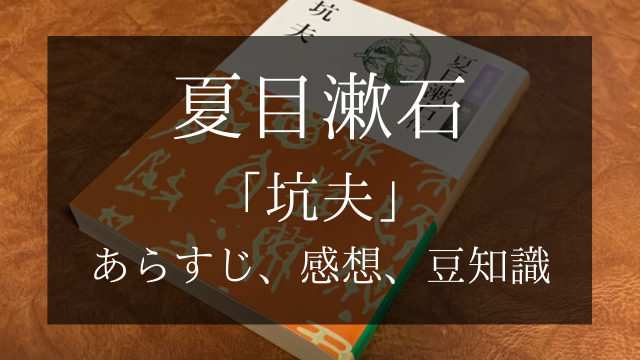夏目漱石の『坑夫』についての記事です。
※こちらの記事はネタバレを含みますので要注意です。
夏目漱石『坑夫』とはどんな小説?
1908年(明治41年)1月1日に朝日新聞に連載開始後、4月まで連載し、単行本としては、1908年(明治41年)9月15日に『草合(くさあわせ)』に、『野分』とともに収録され春陽堂より発行されています。
漱石の朝日新聞入社後の、『虞美人草』に続く2作目の作品で、漱石の家に訪れた一人の青年の体験が元になっており、島崎藤村のピンチヒッターとして執筆することになったと言われています。
作品の順番でいくと『虞美人草』と『三四郎』の間に位置していますが、そのスタイルは大きく異なっていて、小説らしい小説、そして若干飾りが多い(少し過剰?)な『虞美人草』と比べ、淡々と一人の青年の坑夫の体験をつづるドキュメンタリーのような作品です。そして、作品の冒頭では同時代の小説へのアンチテーゼのような文章が多々あります。
そんな作品が『虞美人草』と『三四郎』の間というのが興味深いですよね。ただ単に間に合わせで執筆しただけなのか…なかなか謎の多い作品です。
他の漱石作品のほとんどは、中産階級以上のインテリが主人公で、個人主義や、人間の心理を突き詰めていくようなテーマが大半を占める中で、『坑夫』の世界は、漱石の言う「最下層の世界」であり、しかも、結局、何を言いたいのかは良く分からない。
しかし、青年の思考や感情など、心理描写が妙に生々しく、鉱山・坑夫の描写などもリアルで迫りくるものがあります。
漱石の作品の中でも異色作扱いとなっておりますが、ファンは多いようで、特に村上春樹が坑夫が好きであるという話は有名ですね。なお作中では特に言及はないのですが、舞台は「足尾銅山」と言われています。
『坑夫』のあらすじ
ここでは様々な『坑夫』のあらすじを紹介したいと思います。
恋愛事件のために家を出奔した主人公は、周旋屋に誘われるまま坑夫になる決心をし、赤毛布や小僧の飛び入りする奇妙な道中を続けた末銅山に辿り着く。飯場にひとり放り出された彼は異様な風体の坑夫たちに嚇かされたり嘲弄されたりしながらも、地獄の坑内深く降りて行く……漱石の許を訪れた未知の青年の告白をもとに、小説らしい構成を意識的に排して描いたルポルタージュ的異色作。
※引用元:新潮社
「本当の人間は妙に纏めにくいものだ.」 十九歳の家出青年が降りてゆく,荒くれ坑夫たちの飯場と「地獄」の鉱山,そしてとらえがたいこころの深み――明治41年,「虞美人草」と「三四郎」の間に著された,漱石文学の真の問題作.最新の校訂に基づく本文に,新聞連載時の挿絵を収録.(注・解説=紅野謙介)
※引用元:岩波書店
恋愛関係のもつれから家を逃げ出した青年は、長蔵というポン引きに誘われ、坑夫になることを承諾する。だが、生まれて一度も働いたことのない青年にとって、鉱山の環境は過酷に過ぎた。初さんに連れられ、八番坑のどん底まで案内された青年は付いていくことができず、暗い穴の中に迷い込んでしまう。途方に暮れた彼を救ったのは、屈強でたくましい坑夫、安さんだった。教育を受けた身でありながら、罪を犯して鉱山に逃げ込んできた安さんは、彼に日本の役に立つ仕事に就くことを説く。それでも自分の過去を葬りたい青年は鉱夫になる決意をするが、肺病と診断されて東京へと帰っていく。※引用元:エンサイクロペディア夏目漱石
やっぱり「異色作」、「問題作」という言葉が目立ちますね。
僕が改めてこの『坑夫』について調べているときに気が付いたのですが、岩波書店の『坑夫』の詳細ページには、けっこう気合の入った「編集部からのメッセージ」というものがありました。ほかの夏目漱石の作品にはないもので、ちょっと驚きましたが『坑夫』の岩波文庫旧版は1943年刊行で、70年ぶりの新版として新しく文庫化されたことが理由のようですね。なかなか熱の入った文章ですので一度覗いてみてください。以下、一部抜粋し、引用させていただきました。
銅山への道行き,「新入り」となっての坑道巡り――世間知らずの青年の目を通した,鉱山や独特な坑夫の世界の描写も興味深いものです.ですが物語は筋を語るよりも,揺れ動く感情,連続しない思考,自分でもよくわからない自分の反応への自問自答に密着し,きわめてリアルに描き出します.リアル過ぎて,読んでいる方もなんだか落ち着きません.「読者」の椅子に安心して座っていられない感じです.自分を構成している社会的な要素を全て失ったとき,右も左もわからず,言葉も価値観も通じない世界に放り出されてしまったとき,自分とはなんなのか――その奇妙に肌近い感覚は,設定も時間も飛び越えています. 漱石文学がお好きな方は,『坑夫』以前の,『草枕』 『虞美人草』などとその後の『三四郎』 『それから』にはじまる作品との違い,この不思議な小説がもたらしたターニング・ポイントは何か? という思いに誘われるかもしれません.
※引用元:岩波書店(一部抜粋)
『坑夫』の主な登場人物
以下、『坑夫』に登場する主な登場人物になります。
・主人公の青年
物語の語り手、相当な地位を有つ家の子である19歳の青年。
・長蔵(ちょうぞう)さん
ポン引き、周旋屋。主人公一同を鉱山まで案内する。
・原駒吉(はらこまきち)原さん
飯場頭。坑夫たちをまとめる役。主人公に鉱山、坑夫の仕事について色々説明してくれる。
・初さん
飯場頭の原さんが、主人公のために付けた坑道案内役。
・安(やす)さん
屈強でたくましく、また教養もある人。元は学生で犯した罪のため坑夫となっている。
『坑夫』に関する豆知識
より『坑夫』の理解が深まりそうな?豆知識を紹介しています。
『坑夫』の舞台、足尾銅山について

画像引用元:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
作中には、はっきりとした言及はないものの『坑夫』に出てくる鉱山とは、北関東という位置付けからも「足尾銅山」という認識が一般的です。
その足尾銅山は、今の栃木県に位置し、公害問題を引き起こしたことでも有名ではありますが、かつては日本の国内全産銅の40%以上をも産出する日本一の銅山であり、日本の近代化に大きく貢献したという歴史があります。
足尾銅山の歴史は江戸時代にまで遡り、慶長15年(1610年)に江戸幕府より銅山と認められてから、昭和48年(1973年)まで、なんと!約360年間も、一時休山しながらとはいえ長きにわたって銅の採掘が営まれた日本でただ一つの銅山と言われています。慶長15年(1610年)というと、江戸幕府が開府したのが1603年 (慶長8年)なので、相当昔ですね。
それから十五分ほどしたら町へ出た。山の中の山を越えて、雲の中の雲を通り抜けて、突然新しい町へ出たんだから、眼を擦って視覚を慥かめたい位驚いた。
※岩波文庫版『坑夫』三十九章P119より引用
↑
作中にもあるように、足尾銅山周辺は一時期はかなり賑わっていたようで、景気の良さが伺えますね。
商店街の様子、鉱山夫居住区、本山製錬所、足尾本山駅など以下のサイトに様々な写真や資料があるので是非覗いてみてください。イメージが湧きやすくなると思いますよ!
『坑夫』に出てくる南京米と南京虫について

『坑夫』の主人公が寝泊りする飯場の食事に出てくるのが、「南京米=タイ米」です。
舌三寸の上だけへ魂が宿ったと思う位に変な味がした。飯とは無論受取れない。全く壁土である。※岩波文庫版『坑夫』五十一章P154より引用
↑
のようにとてもまずそうな印象なのですが、僕の幼いころのおぼろげな記憶の中にも「タイ米」を食べた記憶があります。米不足米不足と言われていた時で、記憶が曖昧なのですが改めて調べてみると1993年の米騒動と言われた時にどうやら食べたらしいです。なので、全くもって縁のないものというわけではなかったんですね。
そもそも南京米とは インド・タイ・インドシナ・中国など海外から輸入した米の通称のことで、他にも「南京○○」のように頭に南京がつくものってたくさんあります。
次に紹介する「南京虫」とか、「南京錠」「南京豆」「南京(かぼちゃ)」などです。
これらは中国の南京由来…という意味ではなく、
・南京豆(落花生)→アメリカ
・南京(かぼちゃ)→カンボジア
などなど、簡単に言えば海外からの~という意味なんですね。
粘り気が無くパサパサとしており、日本米(ジャポニカ米)と同じように炊飯器で炊きあげ単体で食べると全然おいしくなく、昔は「南京米」と呼ばれ「不味い米」の代名詞となっていたようです。

※南京虫画像引用元アース製薬
そこでそっと襯衣の間から手を入れて、背中を撫でて見ると、一面にざらざらする。最初指先が肌に触れた時は、てっきり劇烈な皮膚病に罹ったんだと思った。ところが指を肌に着けたまま、二三寸引いて見ると、何だか、ばらばらと落ちた。これは只事でないとたちまち跳ね起きて、襯衣一枚の見苦しい姿ながら囲炉裏の傍へ行って、親指と人差指の間に押えた、米粒程のものを、検査して見ると、異様の虫であった。
※岩波文庫版『坑夫』五十八章P173より引用
『坑夫』の中でも印象的な南京虫。身の毛のよだつようなリアルな描写が特徴的で、思わず自分の布団付近にいないか確認するほどでした(笑)
南京虫は、別名トコジラミと呼ばれていて、今ではこちらの呼び方のほうが一般的なようです。パッと見ると、ダニの一種なのか?と思いますが、実はカメムシの仲間らしいです。
『坑夫』の中にも、主人公が南京虫を潰してその匂いを嗅ぐシーンがありますが、南京虫を潰すと独特のニオイを発するようです。主人公は良い心持になると言っていますね…気になります。日本には海外からの船の貨物についてきたようで、最初は神戸に多くその後日本全国に広まったとのこと。そして、一時は殺虫剤の効果により見られなくなったのですが、近年では、また日本をはじめ海外でも抗体を持った南京虫による被害報告が増加しているようですね。
昼間はベッドや、壁の隅、床などの隙間に隠れていて、暗くなると現れて吸血する…すごく痒くなる。という厄介者のようで、肉眼でも確認できるほどの大きさで、吸血し満腹になると逃げだすそうな。初めて刺される時には痒くないのですが、一回刺されると体内に抗体が形成されアレルギー反応を起こし、赤い湿疹のようなぶつぶつができて、猛烈なかゆみ、場合によっては発熱をも発症するとか…。
『坑夫』の主人公「荒井伴男」について
さて、この『坑夫』の材料を夏目漱石に提供したと言われているのが、「荒井伴男」という19、20くらいの青年。突然現れて、自分の坑夫の体験を小説にしてほしいと頼み込んで来たらしいです。
僕はテレビドラマのほうは未見だけれど、どうやらNHK土曜ドラマ「夏目漱石の妻」第3話の後半に出てくるようですね。
この「荒井伴男」という青年が一時期、夏目家の書生のような形で居候していたようで、木曜会などにも顔をだしてもいたのだとか。夏目鏡子の『漱石の思い出』にこのころの記載(三十二章P207)があり、『坑夫』の主人公が家を飛び出した原因となった、三角関係も青年の実体験だったようで、その相手の娘にも漱石自ら手紙を送ったという逸話も残されています。
結局、荒井伴男は夏目家の親切な対応にも関わらずお金をせびるようになり、嫌になって縁を切られたようですね。
とんでもない男だなーとは思いますが、この青年が夏目漱石に材料を提供しなかったら『坑夫』は世に出なかったことを考えると感謝ですね。
艶子さんと澄江さんについて
『坑夫』において、そもそも家を飛び出した原因となったのが、主人公の女性問題。夏目鏡子の『漱石の思い出』によると、これも実際に青年「荒井伴男」の体験談だったようですが、前作の『虞美人草』との関連性が見られますね。というのも、許嫁がいるのにも関わらず他に恋人を作ってしまったという板挟み状態は、まさに『虞美人草』の小野さんそのままです。
作中では、ぐずぐずと振り返ったりする程度ですが、この家出の原因となった女性関係の問題についても軽く整理したいと思います。あんまり意味はないですが…。
まず、艶子さんと澄江さんについてですが、名前的に、「艶子さん=藤尾」「澄江さん=小夜子」と思ったのですが、
澄江さんはぐうぐう寝ている―どうしても寝ている。自分のいる前では、丸くなったり、四角になったり色々な芸をして、人を釣ってるが、居なくなれば、すぐに忘れて、平生の通り御膳をたべて、よく寝る女だから、是非に及ばない。あんな女は、今まで見た新聞小説には決して出て来ないから、始めは不思議に思ったが、ちゃんと証拠があるんだから慥かである。こう云う女に恋着しなければならないのは、余ッ程の因果だ。随分憎らしいと思うが、憎らしいと思いながらも矢ッ張惚れ込んでいるらしい。不都合な事だ。今でも、あの色の白い顔が眼前にちらちらする。怪しからない顔だ。艶子さんは起きてる。そうして泣いてるだろう。甚だ気の毒だ。然し此方で惚れた覚もなければ、又惚れられるような悪戯をした事がないんだから、いくら起きていても、泣いてくれても仕方がない。気の毒がる事は、いくらでも気の毒がるが仕方がない。構わない事にする。
※岩波文庫版『坑夫』九十二章P268.269より引用
↑
を読むと逆で、「澄江さん=藤尾」「艶子さん=小夜子」だとわかる。どことなく、性格も『虞美人草』の藤尾、小夜子そのままのような気もする…。だからどうなのか?というと困るのだけれど、なんとなくこの設定は『虞美人草』とちょっぴり繋がっているのだな…と思うと、荒井伴男の女性問題のそれぞれの人物の性格もまったく同様だったのか、それとも漱石の手抜き?からくるものなのかというところが少し気になります。
村上春樹と『坑夫』
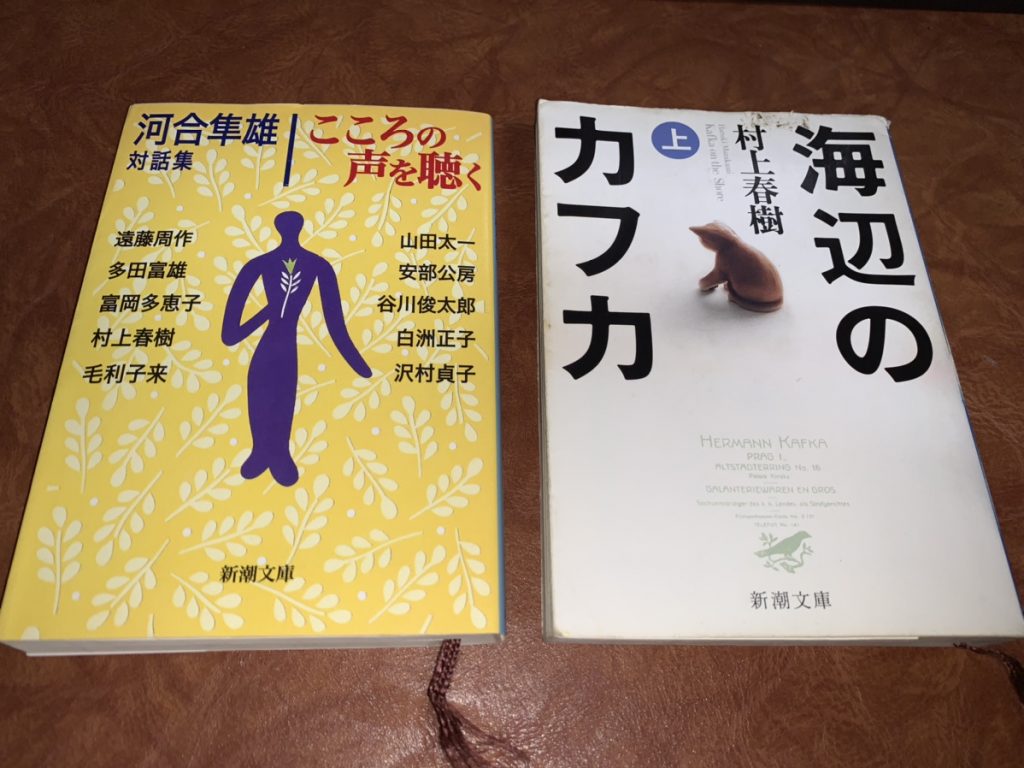
さてこの『坑夫』の話題になると必ず出てくるのが、村上春樹です。夏目漱石の作品の中でも、『坑夫』、『虞美人草』、『三四郎』は村上春樹にとってフェイバリット作品のようですね。
村上春樹の作品の中や、インタビューなどにも多々登場しています。
何を隠そうこの僕も村上春樹の『海辺のカフカ』を読んで『坑夫』を知った口なのです。しかし、最初に『海辺のカフカ』を読んだのは高校生の頃で、その時は夏目漱石の作品だと『坊っちゃん』、『こころ』、『三四郎』くらいしか読んでいなかった頃だと思います。
『海辺のカフカ』の中で『坑夫』に関するカフカ君と大島さんのやり取りのエピソードがあるのですが、当時は「ふ~ん」程度で、あまり気に留めていなかったように記憶しています。(その頃は、バルザックやドストエフスキー、トーマス・マン、サリンジャーなど海外文学ばかり読んでたので…なおさらだったのかもしれません)
しかし、『海辺のカフカ』に出てくるそのエピソードは不思議と心のどこかに、静か~に、ちゃんととどまっているようなエピソードでした。
「何が言いたいのかわからない」けど、そこにはその作品にしかできない心の糸の引っ張りかたがあって、妙に惹きつけられてしまう…僕もこんな風に説明出来たら…と思います(笑)
以下、引用抜粋。
『海辺のカフカ』第13章より「僕」と「大島さん」の会話を引用。
※大島さん
「君はここで今、一生懸命なにを読んでいるの?」
※僕
「今は漱石全集を読んでいます」と僕は言う。「いくつか読んだことのないものが残っていたから、この機会に全部読んでしまおうと思って」
※大島さん
「全作品を読破しようと思うくらい漱石を気に入っているわけだ」と大島さんは言う。
僕はうなずく。
※『海辺のカフカ』村上春樹著 新潮文庫第13章P219
※大島さん
「ここに来てからどんなものを読んだの?」
※僕
「今は『虞美人草』、その前は『坑夫』です」(…)
※大島さん
「一般的に言えば漱石の作品の中ではもっとも評判がよくないもののひとつみたいだけれど……、君にはどこが面白かったんだろう?」(…)
※僕
「それは生きるか死ぬかの体験です。そしてそこからなんとか出てきて、また元の地上の生活に戻っていく。でも主人公がそういった体験からなにか教訓を得たとか、そこで生き方が変わったとか、人生について深く考えたとか、社会のありかたについて疑問を持ったとか、そういうことはとくには書かれていない。彼が人間として成長したという手ごたえみたいなのもあまりありません。でもなんていうのかな、そういう『なにを言いたいのかわからない』という部分が不思議に心に残るんだ」
※『海辺のカフカ』村上春樹著 新潮文庫第13章P220-221
——
そして、大島さんは僕(カフカ君)を高知の別荘に連れていく最中に、フランツ・シューベルトの二長調のピアノ・ソナタについて語り、その楽曲の魅力を語るとともに、僕(カフカ君)が抱いている『坑夫』に惹きつけられる理由を結びつける。
「それはある種の不完全さを持った作品は、不完全であるがゆえに人間の心を強く引きつける、ということだ。たとえば君は『坑夫』に引きつけられる、『こころ』や『三四郎』のような完成された作品にない吸引力がそこにあるからだ。君はその作品を見つける。べつの言い方をすれば、その作品は君を見つける。シューベルトの二長調のソナタもそれと同じなんだ。そこにはその作品にしかできない心の糸の引っ張りかたがある」
※『海辺のカフカ』村上春樹著 新潮文庫第13章P232
他にも、河合隼雄さんとの対話集などでも『坑夫』が好きと明言しているので、かなり『坑夫』がお気に入りのようですね。
夏目漱石というのは明治で近代自我をもっとも強く日本文学に持ち込んだ作家として評価されているし、今でも非常にたくさんの人が読んでいるわけです。彼自身のスタイルも初期から比べてずいぶん変わってきてますね。例えば『虞美人草』と『明暗』を比べるとものすごく違いますね。僕はどっちかというと『虞美人草』とか『坑夫』のほうが好きなんです。それで『こころ』とか『明暗』『行人』、そういう後期のものは近代自我というのが強くあって、その自我と自分の外なる世界とのフリクションというかコンフリクトを彼はすごく綿密に書いていくわけです。その描き方は見事だと思うんだけれど、どうも心にあんまり迫ってこないんですね。皆さんはまた別の感じ方をなさるかもしれないけれど、どうしてこんなことを書く必要があるんだよ、というふうに僕は感じてしまうんです。どっちかというと『虞美人草』なんかのほうが、むちゃくちゃな分、なんだか迫ってくるところがあるんですね。
※引用元:河合隼雄対話集『こころの声を聴く 9章現代の物語とは何か』よりP245
僕は村上春樹も大好きなのですが、『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』のやみくろが出てくる研究所への道のりの箇所や、『ねじまき鳥クロニクル』の井戸のシーンなどに、この『坑夫』の影響?のようなものを感じ取ってしまいます。あくまで主観ですが…。
ちなみに村上作品の英訳を手掛けるジェイルービン氏も『坑夫』の英訳をおこなっており、その序文を村上春樹が書いているそうな…よっぽど『坑夫』が好きなんだな~と思いますねぇ。
『坑夫』に出てくる名言
個人的にグッときた『坑夫』に出てくる名言をまとめたいと思います。
「本当の人間は妙に纏めにくいものだ。」
※岩波文庫版『坑夫』三章P14より引用
自分も他人も簡単に理解なんてできないものだと思います。自分自身ですらも、「あれ、さっきと全然違うこと考えてるな」とか、「おかしいな俺こんなんだっけ…」とか、自分自身にすら矛盾を感じることも多々あるというのに、その上他人様を簡単には理解できないと思う。
よく学校や職場でも、「あいつはああいう奴だから…」とか、「Aさんには○○みたいな対応、Bさんには××みたいな対応がベスト」とか、妙に誰かを判断したり、決めつけることを得意がっている人って多いと思います。もちろんけっこう当たっていることも多いのだけど、時に誰かと接しててまったく予期せぬ別の面がひょっこり出てくることに出くわしたりしますよね?
そういうとき、やっぱり簡単には人を判断できないな~と思ってしまいます。僕なんかは。
「自分が鏡の前に立ちながら、鏡に写る自分の影を気にしたって、どうなるもんじゃない。世間の掟といふ鏡が容易に動かせないとすると、自分の方で鏡の前を立ち去るのが何より上分別である。」※岩波文庫版『坑夫』十二章P42より引用
『坑夫』の個人的な感想
僕が初めてこの作品を読んだのは、すでに村上春樹が『坑夫』が好きという事実を知っていて、『海辺のカフカ』のカフカ少年と大島さんのやり取りを何度も読んだ後だったので、「面白いに違いない」という先入観?がすでに頭にしっかりと染みついた後だった。
なので、フラットに評価できているか?というと難しい。やはり、自分の好きな人、尊敬する人が評価するものは判断が甘くなる。近年のSNSにみられるインフルエンサーとか、芸能人の触れ込みやらが広告となりうるように…影響されて好きになってしまうのは人間だれしもにある要素だと思う。
僕は村上春樹が大好きなので、その村上春樹が好きであるということで無意識に『坑夫』を評価しているのかもしれない。もしかしたら、僕が『虞美人草』好きなのも村上春樹の影響なのか…。
とりあえず、その話は置いておいて、この作品は個人的にはとても面白い作品、興味深い作品だと思う。足尾銅山の坑夫を扱っているけれど、そこまで社会派な作品でもなく、主人公が成長する教養小説でもなく…この『坑夫』の立ち位置がなかなか定まらないところが良いのかもしれない。
ただ、物語好き、ハラハラする展開が好き、という方にはお勧めできないかもしれない。
でも、坑夫や鉱山の情景描写(特に初さんに連れられて、坑道を進むシーン)や、主人公のまとまりのない矛盾だらけの心理描写には、色あせない「何か」があると思う。主人公の意識の流れのような記述に、ハッとさせられることもある。
それと、冒頭でも述べた通り、この『坑夫』が『虞美人草』と『三四郎』との間(厳密にいえば、三四郎の前は夢十夜だけど)というのが、気になります。
・小説らしい小説=『虞美人草』
・小説らしい小説へのアンチテーゼ=『坑夫』
・宙ぶらりんの世界=『夢十夜』
・洗練された明治の教養小説=『三四郎』
装飾過多で若干勢いまかせな『虞美人草』を書きあげ、その反省と「荒井伴男」の体験談をもとに書きあげた『坑夫』で暗くじめじめした「穴」に入り、『夢十夜』で夢心地の状態で「穴」から抜け出そうとし(いや、古い夢を穴の中に置いてきて?)、「穴」から出た漱石は、より洗練された「三四郎」を書きあげる…。
うーん…通過儀礼のようなものだったのだろうか…。
まぁ、ひとつの作品に対してこういう風にわけのわからないことをグダグダ考えるのも、なんか面白い。
しかし、今回はいつにも増して「感想」になっていないですね(笑)